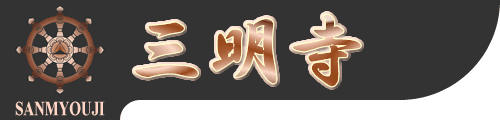
表書きの種類と使い方はどうなっていますか?
御霊前(ごれいぜん)・・・・・・葬儀に際して故人の霊前に供える。御仏前(ごぶっぜん)・・・・・・法事に際して故人の仏前に供える。
御香典(おこうでん)・・・・・・・霊前に香を供えてくださいという意味で使う。
御香華料(おこうげりょう)・・・ 霊前に香や花の代わりに供える金包みに使う。
御供(おそなえ)・・・・・・・・・・・葬儀の際、霊前に供える花や菓子、果物に使う。
御供物料(おくもっりょう)・・・・「御供」の代わりに添える金包みに使う。
志(こころざし)・・・・・・・・・・・・通夜、葬儀の世話役などへのお礼に使う。
御布施(おふせ)・・・・・・・・・・葬儀、法事などでお寺や僧侶へのお礼の金包みに使う。
法要の日とその意味はなんですか?
初七日(しょなのか)亡くなってから最初の供養日。 死亡日を含めて七日にあたる日を近年は葬儀当日にあわせて営むことが多くなりました。
二七日(ふたなのか)/三七日(みなのか)/ 四七日(よなのか)/五七日(いつなのか)/六七日(むなのか)/七七日(なななのか)
七日目ごとに法要をやるのは、これらの日が死者の死後の世界の行き先を決定する「七つの関門」であると信じられ、世界へ行き着くようにとの願いからです。
四十九日(しじゅうくにち)
亡くなってから四十九日間は中陰を漂い、四十九日目にあの世に生を受けるといわれ、忌明けの日であり、死後として運命が決まる日といわれています。
百か日(ひゃっかにち)
一般には内輪で行います。
Copyright 2012 三明寺 All Rights Reserved.
〒 410-0022 静岡県沼津市 大岡 4051
TEL 055-929-2323 FAX 055-929-2324
〒 410-0022 静岡県沼津市 大岡 4051
TEL 055-929-2323 FAX 055-929-2324

